【新連載スタート!】【第1回】 なぜ「繁忙期の人手不足」を解決できたのか 〜ECサイトを持つ地方の食品メーカーの採用「裏」話〜
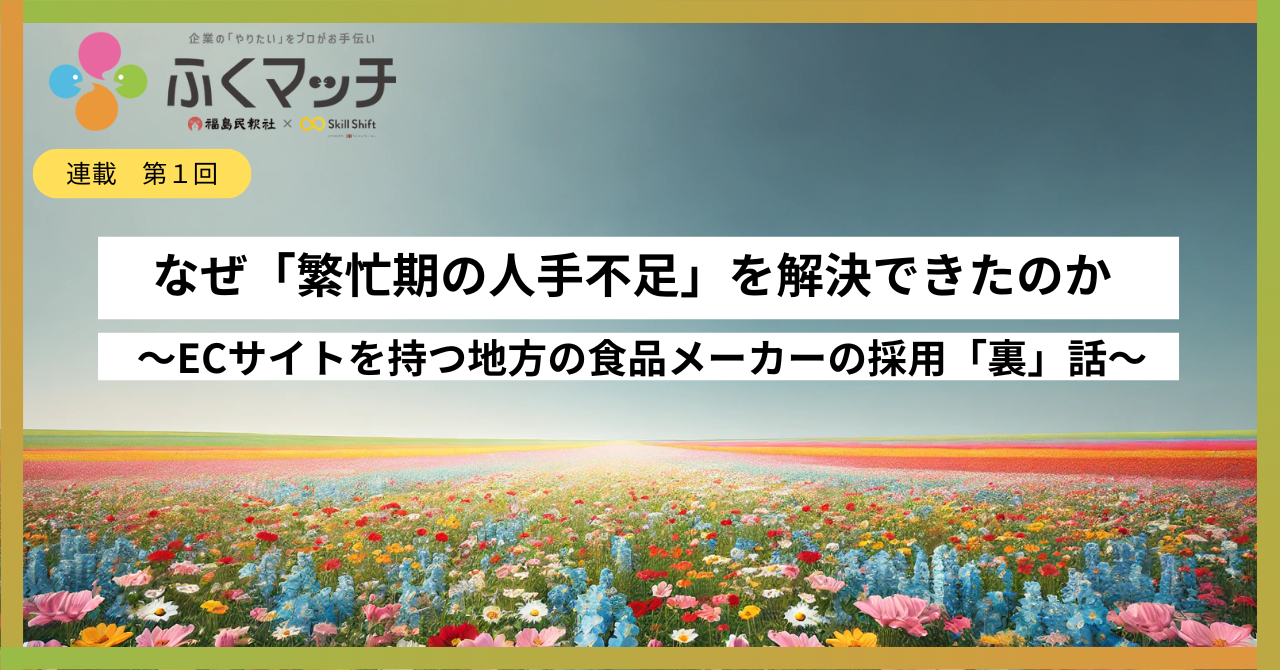
人材不足が深刻化する今、地方企業では「人」の確保と活用が頭を悩ませる課題となっています。本連載は「そんな使い方があったのか」と驚く副業人材の活用方法を全国から集めて、12の物語でご紹介します。
副業採用の現場は「副業者は片手間だから結局は成果が出ない」と言われていた頃から一変しています。「正社員だけの組織運営」から「外部人材を使った組織運営」への切り替えが進む昨今、副業採用に注目が集まっているのです。
といってもそれは「無理難題に今から挑戦すること」ではありませんでした。繁忙期のECサイト運営に毎年苦しんでいた地方の食品メーカーの採用「裏」話をお届けします。
「アドバイスだけされても意味がない」
「外部人材は責任感に乏しい」
そんなイメージはいまも正しいのかを検証する一助となれば幸いです。
------------------------
【3行で読むにはこちら】
(1)地方の老舗菓子メーカーA社がお歳暮シーズンの2か月間だけ副業人材を起用した。売上120%アップ・クレーム半減という驚きの結果を実現するまでの物語を紹介する
(2)「正社員かアルバイトか」という二択を超えた「必要な時期に必要なスキル」を確保する。この新しい採用戦術が、地方企業の経営課題を解決するカギになっている
(3)副業人材の活用は単なる「人手確保」を超える。社内の若手社員が外部のプロから直接学べる「知識移転の機会」としても機能する
------------------------
以下リンク(note)より、記事をご覧いただけます。
関連リンク
- 記事はこちらhttps://note.com/fukumatch/n/n4cf4f077d6f4(外部サイトへ移動します)
